「勉強についていけない」と悩む新人理学療法士のあなたへ。
その悩みは、あなたの能力や努力が足りないからではありません。
それは、学校の「勉強」と臨床の「勉強」の“質”が根本的に違うからであり、その「学び方の優先順位」 をまだ知らないだけです。

学校で習った知識と、目の前の患者さんがうまく結びつかない…
何から勉強すればいいか、優先順位が分からない…
これらの悩みは、かつての私自身が通ってきた道です。
私が指導する新人たちも、毎年必ず同じ壁にぶつかっています。
この記事は、多くの新人を指導してきた指導経験に基づき、「臨床現場で本当に役立つ、最短の学習ロードマップ」を具体的に指導します。
単なる勉強法の紹介でははなく、「ついていけない」というあなたの不安が消え、自信を持って患者さんに向き合える「次の一歩」が明確になります。
- 新人PTが「勉強についていけない」と感じる本当の原因
- 臨床で「独り立ち」するための最短学習ロードマップ(3ステップ)
- 多忙な新人が「勉強の時間がない」を克服する、具体的な時間のつくり方
- 勉強のモチベーションが維持できない時の、マインドセット
なぜ新人理学療法士は「勉強についていけない」のか? 2つの根本原因を解説
あなたが「ついていけない」と感じる原因は、大きく分けてこの2つの「壁」のどちらか(あるいは両方)です。
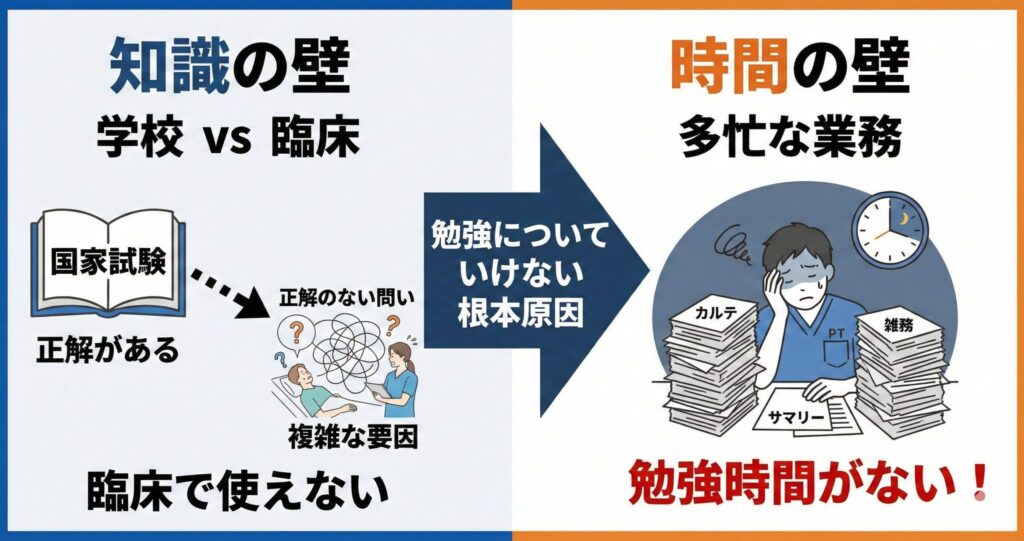
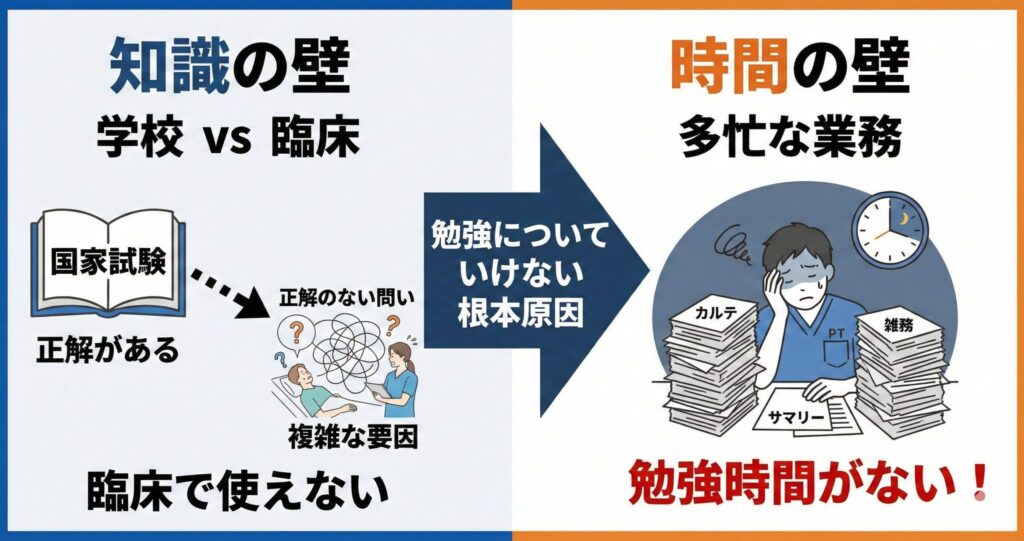
この2つの壁は、根性や努力だけで乗り越えられるものではありません。



まずは「壁の正体」を正確に理解することから始めましょう。
原因1:「知識の壁」 学校の勉強が臨床で“使えない”という悩み
新人PTが最初にぶつかる、最大の壁です。
学校での勉強は、「解剖学」「生理学」といった科目ごとの勉強であり、「国家試験」という明確な“正解”がある勉強でした。
しかし、臨床現場(病院)で求められるのは、その逆です。
目の前の患者さんは、「解剖学の問題」や「運動学の問題」を抱えているわけではありません。
学校の勉強が臨床で使えないのは、様々な要因が複雑に絡み合った「正解のない問い」を解かなければいけないからです。





画像のように、思考を転換させましょう
原因2:時間の「壁」 日々の業務で“勉強の時間がない”という焦り


第二の壁は、物理的な「時間」の問題です。
カルテ入力、サマリー(申し送り)の作成、カンファレンスの準備、そして日々の雑務…。
新人時代は、これらをこなすだけでも精一杯です。



勉強しないと、という焦りだけが募るけど、疲れて寝てしまう…
この状態が続くと、「勉強できない自分はダメだ」という自己嫌悪に陥りがちです。
時間の「壁」問題の本質は、「効率化」と「優先順位付け」の技術です。
新人が陥りがちなのは、「完璧主義」の罠です。
(例:カルテやサマリーに、必要以上に時間をかけすぎてしまう)
この「時間の壁」をどう乗り越えるか。
その具体的なテクニックは、後半の「時間捻出術」の章で詳しく解説します。
「新人PTは時間がなくて当たり前。だからこそ“戦略”が必要だ」と認識してください。
新人理学療法士が「勉強についていけない」を克服する“3ステップ学習法”


「知識の壁」と「時間の壁」。
この2つを同時に乗り越える、最も効率的で実践的な学習法をお伝えします。
結論からいうと、 新人の勉強は「本」からではなく、「症例(目の前の患者さん)」から始めてください 。
これが、多くの新人を指導してきた中で、最も早く「独り立ち」するPTに共通する学習法です。
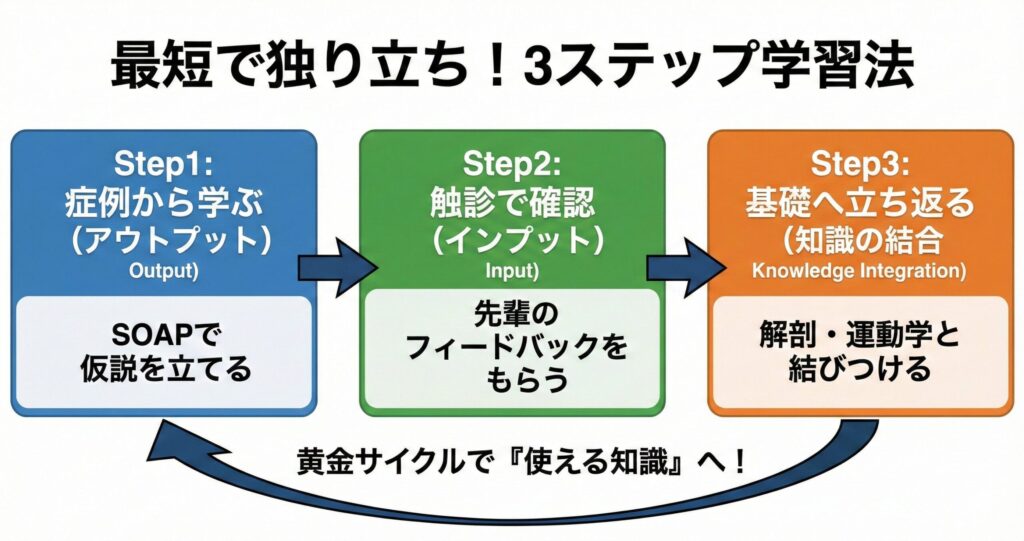
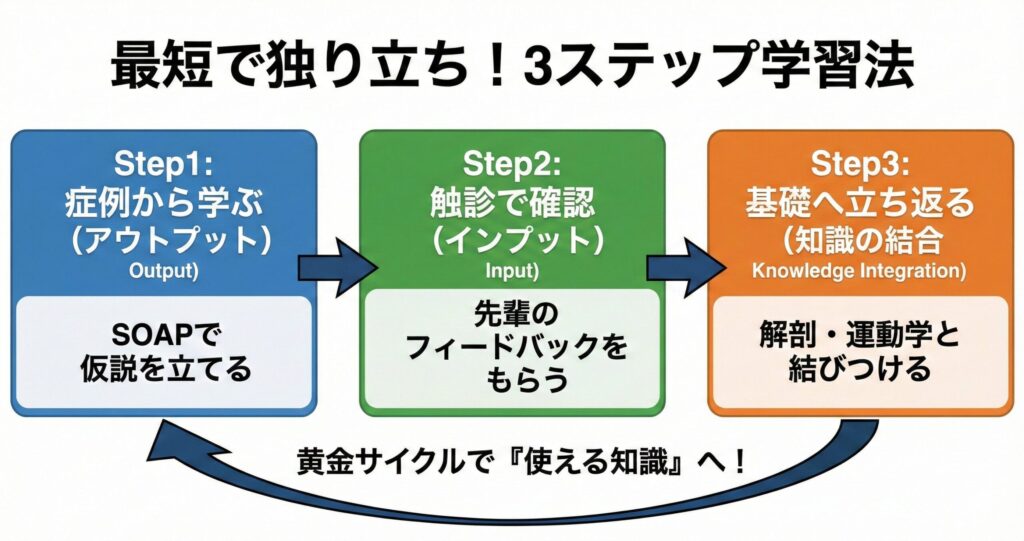
Step1:症例(患者)から学ぶ
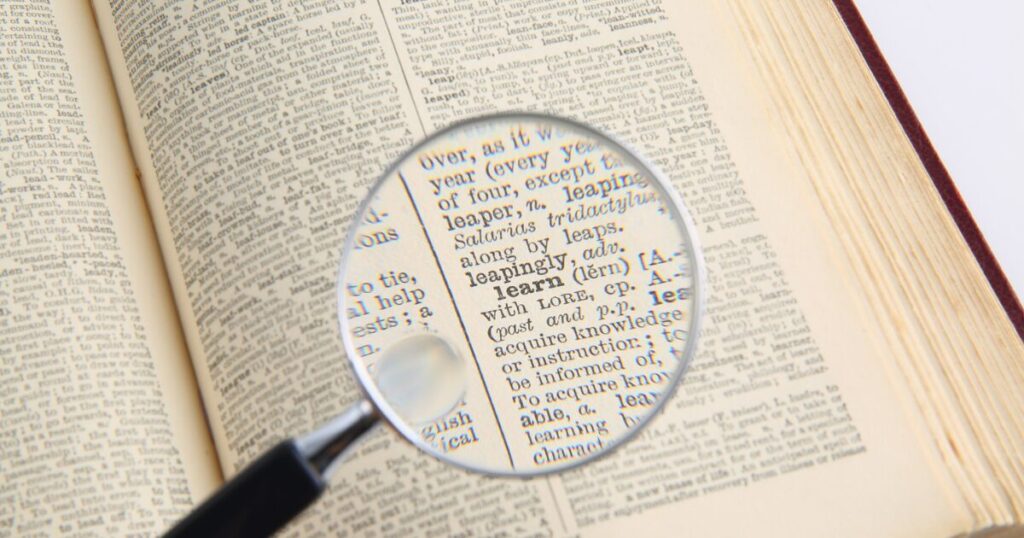
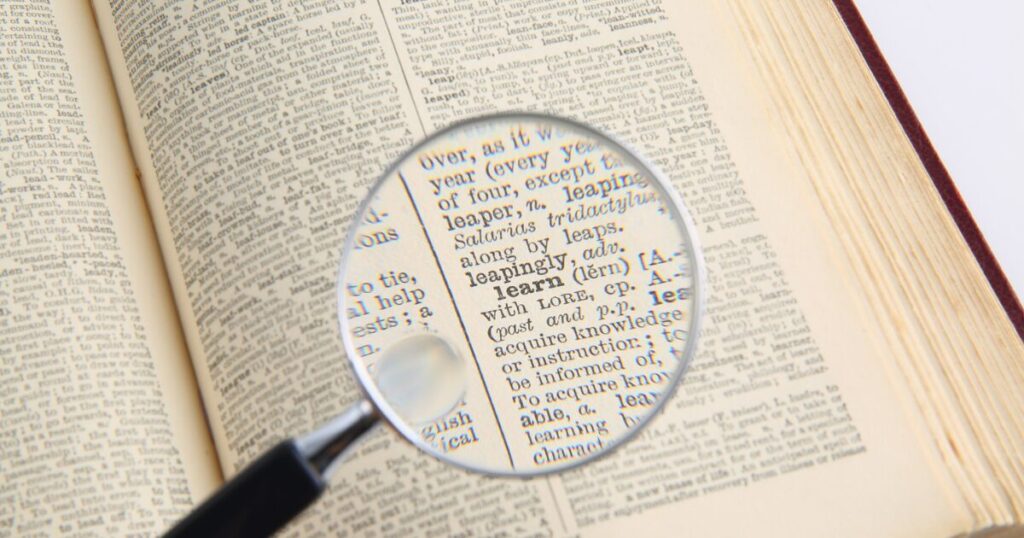
何から勉強すればいいか分からない、という悩みへの最適解がこれです。
- なぜ「本」からではなく「症例」から学ぶべきか?
-
多くの新人が、不安から分厚い「解剖学」や「運動学」の教科書を1ページ目から読み返そうとして、挫折します。
それは、学校の「体系的な勉強」のクセが抜けていないからです。



臨床で求められるのは「仮説検証型」の勉強です。
- 本から入る勉強(NG):
-
- 時間がかかりすぎる。
- 臨床と結びつきにくく、記憶に定着しない。
- 症例から入る勉強(OK):
-
- 「なぜ?」という目的が明確なため、学習効率が圧倒的に高い。
- 学んだ知識が「使える武器」として即、臨床に活きる。



具体的な実践方法はありますか?
「症例から学ぶ」とは、具体的には「SOAPを自己学習ツールとして使う」ことです。
SOAPを単なる「業務記録」で終わらせてはいけません。
- S(Subjective / 主観的情報):
- 患者さんの「訴え」から、「何に一番困っているのか?」という最大のニーズ(=勉強のゴール)を明確にします。
- O(Objective / 客観的情報):
- 評価結果(ROMやMMTなど)。ここで「なぜこの可動域制限が起きている?」という「仮説」のタネを見つけます。
- A(Assessment / 評価):
- ここが最重要。 Oで見つけた「仮説のタネ」を、あなたの知識(解剖学・運動学)と結びつけ、「〇〇が原因で、××が起きている」という仮説を立てます。
- P(Plan / 計画):
- その仮説を「検証」するための治療プログラムを立てます。
この「A(仮説)」→「P(検証)」のサイクルこそが、新人PTにとって最強のアウトプット学習です。
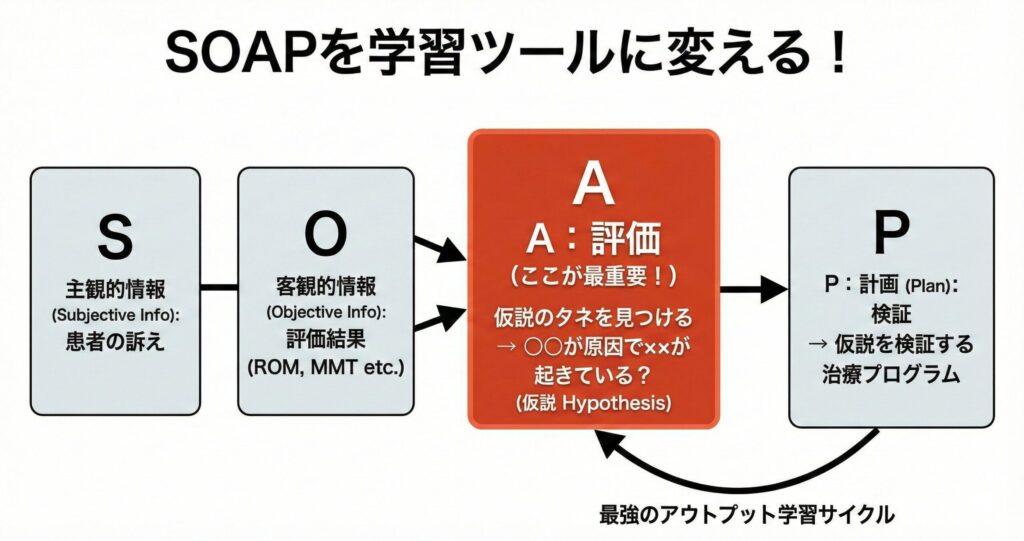
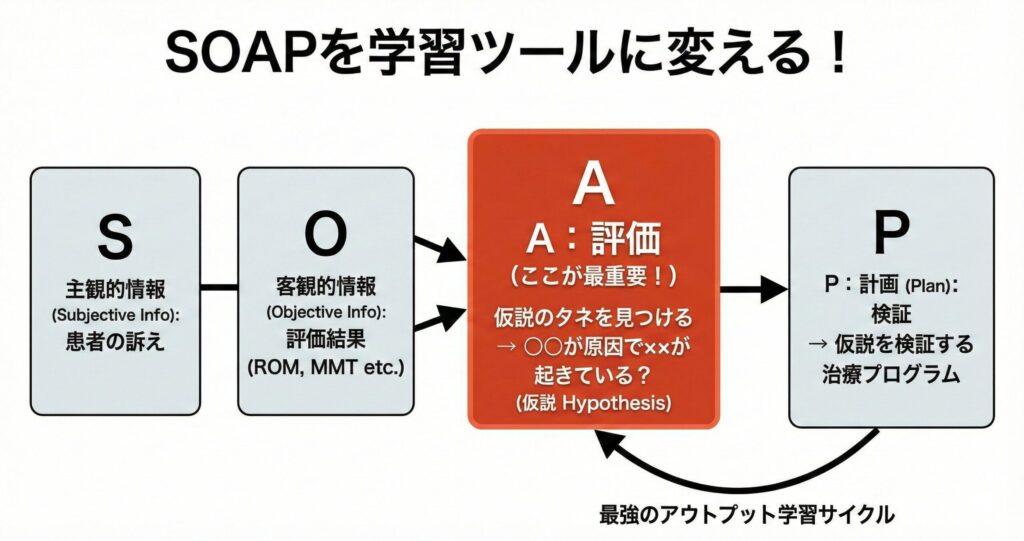
Step2:「触診のコツ」を先輩から盗む(インプット)


Step1の「O(客観的評価)」の質を担保するのが「触診」です。
触診は、評価の土台です。
これが曖昧だと、Step1の「仮説(A)」そのものが間違ってしまいます。



こればかりは独学では絶対に上達しません。



先輩に質問するのって、緊張しちゃうんですが⋯
「忙しそう」と遠慮して質問に来ない新人よりも、「1分だけください」と具体的に質問に来る新人の方が、100倍伸びます。
- 悪い質問(NG):
-
- 「触診が分からないので、教えてください」(←漠然としすぎている)
- 良い質問(OK):
-
- 「〇〇筋の走行を、AとBの2パターンで考えたのですが、どちらの認識が近いですか?」
- 「今、〇〇(骨指標)を触っているつもりですが、この位置で合っていますか?」
Step3:「基礎(解剖学・運動学)」に立ち返り、臨床と知識を“結びつける”
「仮説(A)」を立てる時、必ず「知識不足」に直面した瞬間こそ、あなたが「本(基礎)」に戻る絶好のタイミングです。


(例)「この患者さんの歩行が不安定なのは、なぜ?」
→ Step1(仮説):中殿筋がうまく機能していない?
→ Step3(基礎):ここで初めて「解剖学の教科書」を開き、中殿筋の「起始・停止・走行・作用」を再確認する。
→ (気づき):「なるほど、この走行だから、このタイミングで機能しないと歩行が不安定になるのか!」
「勉強の時間がない」新人PTのための時間のつくり方
「勉強の時間がない」という新人PTの焦りは、痛いほど理解できます。
「知識の壁」を越えようにも、そのための「時間」がなければ、どうしようもありません。
ですが、時間は「作る」ものです。
以下の3つの鉄則で「時間」を作り出す工夫してみてください。


鉄則1:「やらないこと」を決める(ダラダラ残業をしない)
新人PTが最も時間を浪費するのは、「完璧なカルテ」や「完璧なサマリー」を目指してしまうことです。
私が指導する新人の中にも、先輩に見せるサマリーの『てにをは』を30分も悩んでいたり、すでに評価が終わっているのに、カルテ入力の『書き方』で延々と残業したりする人がいます。
カルテは『伝わること』が最低限の目的であり、芸術作品ではありません。
『8割の完成度で、まず先輩のチェックを受ける』『◯時以降はカルテ作業をしない』
など、自分ルールを決めて“やらないこと”を明確にすべきです。
鉄則2:「朝活」をルーティン化する(30分でOK)


疲労困憊の「夜」の1時間より、頭がクリアな「朝」の30分の方が、勉強の効率は3倍高いです。



日々の業務に左右されない「朝」こそ、唯一確保できる「貴重な時間」です。
早起きは苦手と思うかもしれませんが、目的(=今日の臨床で昨日学んだことを試す機会)があれば、不思議と起きられるようになります。
鉄則3:効率化ツールに課金する(時間をお金で買う)


「勉強の時間がない」を解決する最後の手段は、「時間をお金で買う」という発想です。



私も効率化のためにはツールに課金します
時間は誰に対しても平等であり、有限です。勉強を効率良くするためには、惜しみなく課金しましょう。
- 臨床知識の体系化に(リハノメ / リハデミー)
- 勉強の「質」と「効率」を最大化するなら、動画学習サービスが最強です。
- 勉強アプリは通勤時間や休憩中、スマホ一つで体系的な臨床知識を学べるのは、本での学習にはない圧倒的なメリットです。
- 学習のモチベーション維持に(スタディプラス)
- これを使うと、あなたの「努力」がグラフになり、「これだけ頑張った」という自信に繋がります。
Q&A
学習法と時間術を指導しても、「モチベーションが続かない」という悩みを抱える人が多くいます。
モチベーションの維持は、新人PTにとって永遠の課題です。
他にも様々なよくある悩みについて回答していきます。
- 同期と比較してしまい、焦ります…
-
無意味なので、今すぐやめてください。
同期は「仲間」であって、「比較対象」ではありません。 成長速度は人それぞれ、得意分野も違います。大事なのは「昨日の自分」より一歩でも成長しているかどうか、それだけです。
比較するなら、「あいつ、あの手技を覚えたのか。じゃあ俺は、この評価を完璧にしよう」というように、お互いを高め合う「健全な競争」としてのみ、比較してください。
- 勉強会に行くべき? 行きたくない…
-
目的がないなら、行かなくていいです。
「勉強会に参加すること」=「勉強している」ではありません。 インプット(勉強会)は、アウトプット(臨床で使う)して初めて「勉強」になります。



「明日、〇〇さんのために絶対この技術を盗むぞ」と決めて参加するほうが、普通に参加するより100倍価値があります。
- 勉強の「やる気」がどうしても出ません…
-
「やる気」は行動の「結果」、後からついてくるものです。
「やる気が出たら勉強しよう」では、一生勉強できません。 逆です。「勉強(行動)するから、やる気が出る」のです。
まとめ
「勉強についていけない」と悩む新人PTの皆さん。
この記事で、私が伝えたかった「本質」を、最後にもう一度繰り返します。
勉強は「本」からではなく、「目の前の患者さん」から始めてください。
- Step1: 症例(SOAP)で「仮説」を立てる。
- Step2: 触診で「事実」を集め、フィードバックをもらう。
- Step3: 仮説と事実を「基礎(本)」で結びつける。
あなたが今日学んだ「知識」と「技術」は、明日の患者さんのQOLを向上させ、そして何より「患者さんの安全を守る」ためのものです。
この「3ステップ学習法」を実践すれば、あなたの臨床は必ず変わります。
まずは、明日担当する患者さんについて「なぜ?」を一つだけ見つけることから、その「次の一歩」を踏み出してみませんか。

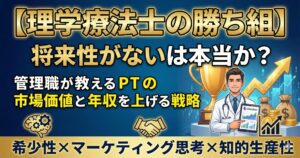


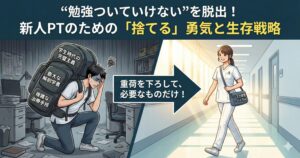
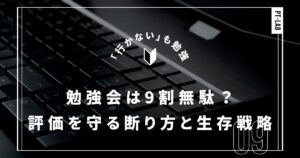
コメント